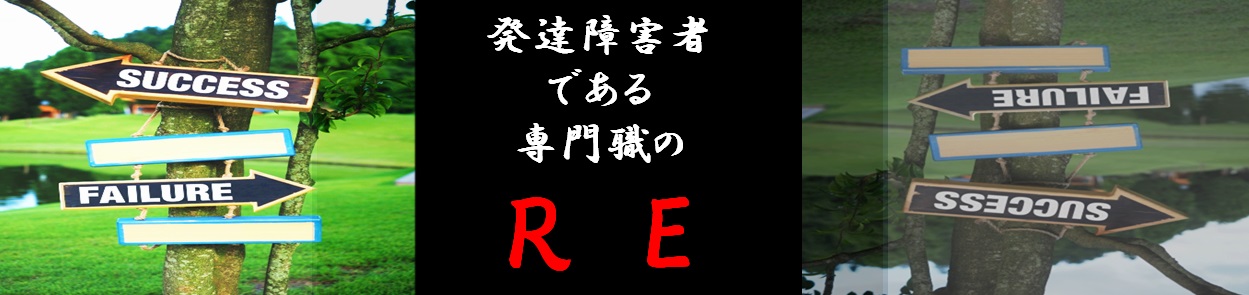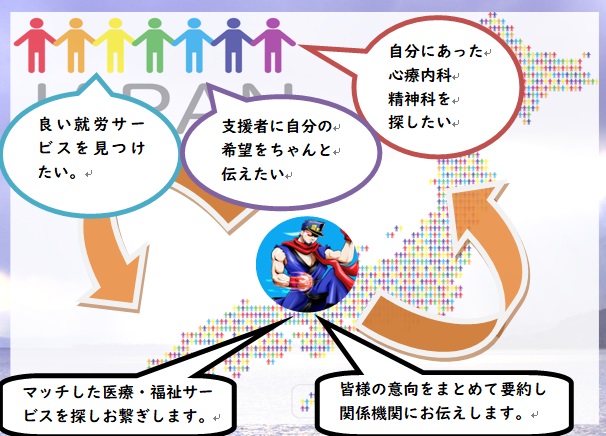発達障害が二次障害として併発しやすい症状、類似して含まれやすい症状に双極性というものがあります。
双極とは、、、
気分の高揚、万能感、攻撃性が増す躁(そう)状態と、
気分の落ち込み、現実以上の悲観的認知、死にたいと思う鬱(うつ)状態を繰り返す症状です。
社会生活、特にクローズ就労(障害を隠して就労)を行う上では、双極症状との付き合い方は非常に重要です。


はじめまして、RIKEIです。
京都大学で生物学を専攻しておりました。
その見地からリファレンスのある発達特性、双極性症状への処世術をお伝えします。
双極性を持ちながらクローズ就労でうまく立ち回るには?
多くの方が双極性疾患を持ちながらクローズの状態で仕事をこなしていくのは難しいと思っているのではないでしょうか?
言うなれば仕事をそつなく継続しながら、周囲との関係性を乱し過ぎず継続するだけですが、それが容易にできていたら誰も苦労はしませんよね。
医師から双極性障害Ⅱ型・発達障害診断を受けながらもクローズで働いていた筆者の経験から、職場でうまく立ち回れるポイントをお伝えします。



発達障害ランキング
にほんブログ村
躁(そう)転・鬱(うつ)転とは?
筆者の場合を例に挙げてみましょう。
・対話が苦手であるにも関わらず、積極的に交流しようとする。
・睡眠時間が明らかに短く目覚めが良い上、眠気がない。
・落ち着きがなく集中力に欠けてしまい、色々なことに手を出しては非効率な結果になってしまう。
・自分の考え全てが思い通りになるだろうと誇大妄想してしまう。
・希死観念(死にたいという想い)が常に存在している。
・何を考えても悪いことばかりに結びついてしまう。
・日光や明るい場所を嫌う。
・些細な雑音や環境音が非常に気になる。
・極端に人と接触したくなくなる。
・身体が重く、動けない。
双極性の症状は、上記の浮き沈みを繰り返すのですが、症状には個人差があり、躁・鬱から次のエピソードまでの間隔においても1日単位の方から数年単位の方まで存在し、非常に幅があります。




鬱(うつ)状態に支障があるのは、わかりやすいと思いますが、
実は人間関係を壊したり社会的立場をなくす行動は躁(そう)状態の時に起こりやすいので注意が必要です。
万能感が増加すると「自分が全て正しく他人はバカに見える」状態になります。「バカに正しい事を教えてやっている!」と攻撃的で他者への敬意を配慮出来ない言動や態度が表れることもあります。
優秀で実績のある人は、客観的な実績があるだけに自覚をし難く、無自覚な躁転の勢いで他者を激しく傷つけていることがあるのです。
社会生活においては、トラブル、関係悪化、孤立化の原因となり、自覚とコントロールが必要な課題なのです。
躁鬱(そううつ)のサインは?自分をデータ化する
「頭痛がする」「身体が重い」「喉が痛い」などの身体のサインは、非常に感じ取りやすい不調サインです。
そして、不調を自覚していれば、それ以上体調が悪化しないよう体調管理や、勤務内容についても注意を払う方が多いのではないでしょうか。
双極性疾患においても上記のようなサインを常に自身が把握することが、クローズ就労において重要なポイントの一つです。
具体的にデータ化させたい項目は、以下の点です(一部抜粋)。
躁転している場合、平常より短時間睡眠となり目覚めもスッキリしている傾向がみられます
平常を基準として
躁転している場合は活動量が異常に増え疲労しやすくなる一方で、
鬱転している場合は活動量が極端に低下する傾向がみられます。
1日の生活を振り返り、自分が現在どの状態(躁鬱の波)に位置しているかを日々確認しておきます
以上の内容をデータ化させ継続的に自己を管理することで、自身の双極の波や躁転・鬱転する兆候が見えてきます。
データ化といっても、○×・5段階中の評価・日記など、ご自身が管理しやすい方法であれば何でも構いません。
自身の状態の位置が把握できると、予防的な体調管理や勤務を行うことができるようになるでしょう。
躁・鬱・自分の体調変化のサインを把握する
筆者は、1日の中で上記の傾向や予兆を意識しながら過ごしています。
まるで自分が医者になったかのように、自分自身に問いかけ、日々の状態を「経過観察」しています。
すると、自身が体調を崩す「きっかけ」が必ず表面化されてくるでしょう。
その「きっかけ」自体が、睡眠時間や活動量とリンクしていることが非常に多いのです。
筆者は、その「きっかけ」や「サイン」を受け取り次第、休みの態勢に入ります。
・精神状態の不調を早期に自覚する。
・人とむやみに会わない様にする。
・外界の環境を調整する。
・意識して身体を休める。
などの様な対策をして社会生活への影響を減らします。
このように自身の症状・体調変化のサインを少しでも把握しているだけで、その先の体調予測や休み方がわかるため、安心感が芽生えます。
また、これまで抱えていた双極性疾患における精神的ストレスの軽減にもつながるため、安定した就労態勢を整えやすくなるでしょう。
意識するだけで物事の見え方が変わるということは、双極性疾患にも当てはまります。
まずは、ご自身の1つずつ、自分自身とゆっくり向かい合い、生活リズムと双極傾向を自覚する時間をとってみてはいかがでしょうか。
著者紹介:Corgison Rikei
京都大学大学院理学研究科卒、時間生物学専攻。多数のアルバイトと研究職を経てから、現在は実体験と知恵知識をもとに、幅広い層に向けたライフハックを届けている他称研究者。精神障害者当事者でもあり、ユニバーサルな環境作りを基礎理念として活動している。論理的クリエイターとして様々な情報発信中。凸+凹=◇≠□。趣味はホモ・サピエンスの研究。双極性障害II型/発達障害/精神手帳2級
Twitter:@corgison
Web:https://corgisonrikei.wixsite.com/kimagureya
Mail:kimagureya.online@gmail.com




RIKEIさんありがとうございました。
双極性障害という診断を受けていない方でも、発達特性に類似した特性を持つ方は多くおられます。
現在、ご自身を苦しめている人間関係、不利となっている社会的立場の中に、その様な原因はなかったでしょうか?
もし、あったとしたら、、、
躁転、鬱転特徴に心当たりを感じられた方がおられたとしたら、、、
気づいた時点から自身の特性に向き合い対策をしていけばいいと思います。
また、ご自身の体調変化を知る為には、以前に紹介させて頂いたスマートウオッチが有効なツールになると思いますので、ぜひご参照ください。



発達障害ランキング


ADHD(注意欠陥・多動性障害)ランキング
にほんブログ村