
・発達障害者の子育て問題
私には就学前のこどもがいます。親として力不足の私の育児は、保育所の先生と二人三脚でやっと行ってきました。
自分が一度子育てを失敗した経験、自分の障害受容から、保育所の先生方には自分をオープンにしていました。
そして気になることがあると率直に相談しながら子育てを行ってきました。
保育所の先生方の発達障害理解については驚きました。世間よりは5年ぐらい早い認知度で発達障害特性を理解し、ナチュラルに受け止め、おおらかに特性を見守り、成長を促す視点があったのです。
そして、保護者自身が抱える困難さについても相談支援を行い、子育てを支える役割を果たしてくれました。
保育所とは単なる託児所ではなく、地域の子育てを支える社会福祉施設なのです。
保護者が胸襟を開いて先生方に子育ての悩みを相談すればこどもの個性を見て専門的な見地で育児サポートがうけられる貴重な社会資源です。

・学校教育に感じた選別
対して、先日、小学校の入学説明会がありました。
その内容を聞くと保育と教育の違いを感じました。まず、最低限「身辺の自立」が求められます。
登下校、着替え、トイレ、時間内の食事、配膳など、当たり前に自分できて、時間割の中で教育カリキュラムにそった勉強を進めていくこと。
保育所ではできる子、できない子が居ても成長のバラつきと見守り、フォローされていた様な部分に、一定の出来ないといけないラインが引かれて、一つのふるいが設けられたように感じました。
そのラインについてこれない児童は「特別支援級」のフォローを受けて少人数、個別に生活支援、学習支援が行われていくのだと思います。
淡々と語られる小学校の内容に私は内心不安を感じました。
保育所は発達の凹凸も障害も包み込むように受け入れて同じ教室で過ごしていました。園児同士のもめごと、ケンカもコミュニケーションの機会として、物事の合理性、感情の整理、自己主張の方法を保育士が仲介して学ばせてくれていました。
何も出来なかった赤ちゃんから、出来ることが少しづつ増えていくこどもの成長過程を見守り、人として生きる基礎を与えてくれていたのです。
一方小学校のカリキュラムに入ると、ある程度自分の内面的な問題は片付け、身に着けて、集団での教育カリキュラムの波に乗って、ついていかないとふるい落とされてしまうと感じました。

・入学までの発達の課題は!?
その様な不安を感じた足で保育所で担任の先生と個人面談を行いました。
小学校で求められる「身辺的自立の面」「集団行動」「対等な自己主張」「心身のバランス」「自己肯定感の育ち」そして、年齢からみた「発達の凸凹」について、率直にたずねました。
私は自分が親になりきれていない部分を感じていました。時折、衝動的に叱ってしまったり、激しい夫婦ケンカを見せてしまったり、生活習慣を乱してしまうなどの逸脱を感じて、反省をしながら育児書を学んだり、保育所のサポートを受ける子育てをしていました。
しかして、担任の先生の答えは、、、
小学校に入るまでに、身に着ける習慣はしっかり育ち、自己肯定感も育ち、主張もと出来て、発達の偏りは特に感じられることなく育っていると答えて貰えました。
本当に私の親としての機能不全な点を保育所で補って貰えてここまで育ててきて頂いたおかげだと感謝しました。

・子育て困難な機能不全親だと自覚しながら
私の親としての機能不全とは謙遜や卑屈な見解ではなく、間違いなく私は機能不全養育者(毒親)でした。
その葛藤については前ブログで掲載しています。

リンク先:発達障害者である専門職のブログ
私達の子育ては初めから福祉的なフォローを受けて始まりました。
私の妻はパニック障害を持ち、産前の和痛分娩で少し後遺症が残り、1週間立ち上がれない状態になりました。その後産後うつを発症したために保健師と相談して心身のフォローを必要としました。
私が不在の間には祖父母や近隣の協力者に支援を頼み、ローテーションを組んでケアマネジメントを行い産後の危機を乗り越えました。
そして、こどもが生まれた翌年に私は突然、長年勤めていた仕事から切られてしまいました。
詳細は以下記事です。

リンク先:発達障害者である専門職のインディペンデンス
関連記事:雷鳴の夜からの再生
必死に再就職をした後に発達障害の診断を受けて、自分を見つめ直し学び進める中での子育てでした。
自分の幼少期には母が居ず、家庭のロールモデルもなく、自然な人生経験の上から伝えられるコミュニケーションスキルもありませんでした。
不足した経験は知識として、児童書・育児書などのなかから学び、自分を振り返りながら子育てを実践していきました。

リンク先:発達障害者である専門職のインディペンデンス
親としての機能不全は、細かく保育所の先生に伝えて助言をもらい、保育所で私達が出来ない養育をして貰いました。
そんな「社会的サポート」と「親として学ぶ猶予」が与えられたおかげで、やっと親になる準備が出来て就学期を迎えられるようになりました。

・出来るようになる過程を見守る視点
学び進める中で「発達障害の理解」と「保育の視点」は非常に相性が良いと感じました。
年齢による発達段階を知ることは発達の凸凹をアセスメントする手がかりとなりました。
そして障害福祉の世界の様に下手に「障害診断」「知能テスト結果」が先にあるのではなく、フラットに「成長する順番に個性がある」とあたたかく見守られるのです。
つまり、発達段階を「出来ない」という視点ではなく、乳児期から見て「出来ることが増え成長している過程」と見まもるのです。その視点は「支援の可能性」に感じられました。
例えば、小学校2年生の段階で「3歳の頃に獲得し損ねていたコミュニケーションスキル」があったとしても、その部分に対して3歳児の保育的な促しや働きかけを与えると成長し直していけると思いました。
その様な、理解ある環境に恵まれたおかげで、私達が持つ家庭の機能不全は補われて、なんとか子育ての体裁が保ててこどもの就学期を迎えられる様になったのです。
昨年は、保育園への感謝を込めて、PTA会長になったのですが私の障害を知っている先生方には、ひやひやと思われながらの任期だったと思います。
案の定、私の保育園への感謝の重さは、PTAの任務を逸脱することもあり、一緒に取り組む役員のみなさまには負担をかけて、空回りをしてしまうことも多々ありました。
PTAとして1年間決まったルーチンをこなすだけの仕事に「社会福祉」と「子育て支援」という要素を盛り込もうとし過ぎたのです。
そんな、ドタバタなPTA会長時代のお話はまた別の機会にさせて貰いたいと思います。
関連記事:



発達障害ランキング
にほんブログ村
にほんブログ村


関連記事:発達障害者である専門職のインディペンデンス


関連記事:発達障害者である専門職のインディペンデンス


関連記事:発達障害者である専門職のインディペンデンス
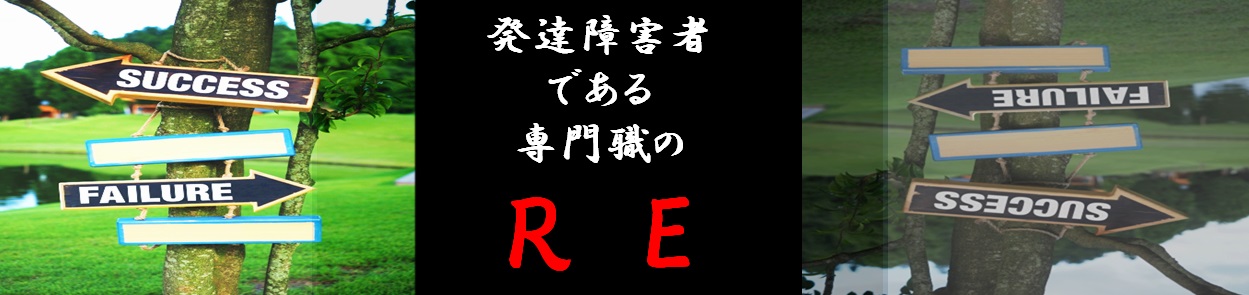






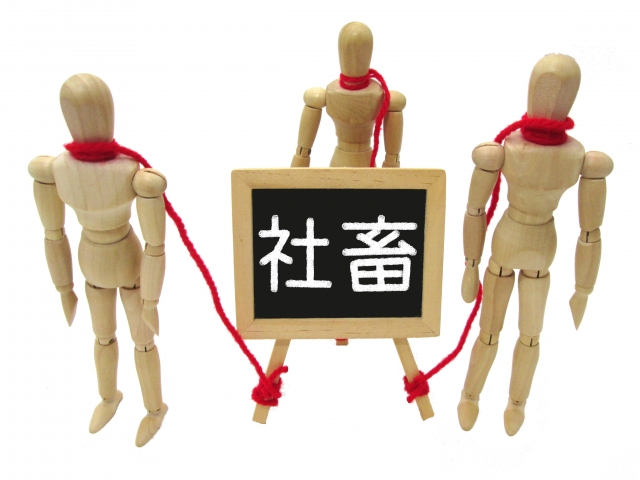
コメント
[…] 続・発達障害者の家庭問題・子育て困難 […]